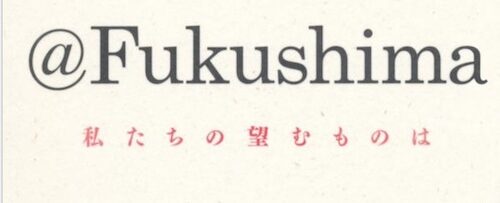◆トルコを舞台にした人と人、人と文化の出会いの物語
人と出会うことがままならない今、東西文明の十字路のまちを舞台に、人と出会う歓びをテーマとした絵本『海峡のまちのハリル』(絵・小林豊、三輪舎)を12月21日に上梓した。文はわたし・末澤、絵は画家の小林豊さん。絵本という表現手法ではあるが、私にとっては、出来事の背景を深堀りして伝えるスローニュースの取り組みの一環でもある。

『海峡のまちのハリル』(文・末澤寧史、絵・小林豊)
私がフィールドとするトルコには、興味深い「世界のはじまり」がたくさん眠っている。オープンカフェ、大学、製鉄、神殿、サンタクロース……。冒頭から脱線するが、今まさにクリスマスで大忙しのわれらがサンタクロースは、トルコ国内で南国リゾート地として知られるアンタルヤ県のミラが発祥地と言われている。4世紀ごろに実在したとされる聖職者のニコラオスが、死後も船乗りや子どもを守る聖者として敬われてきた。貧しい子どもに施しを与えたという伝承がヨーロッパに広がり、時を経てあの赤い服を着た、白髭のサンタクロースに変容していったという説がある。
今回の絵本で私は、題材の一つとして「マーブリング」という絵画手法を紹介した。これも製紙法とともに中国で生まれたとされるものの、現在のように世界中に広がるうえでは、東西文明の交差点であるトルコの地が果たした役割が大きい。
マーブリングは、トルコでは「エブル」と呼ばれ、伝統絵画として近年再評価されている。水面に絵の具で描いた波模様を紙に写しとるもので、美術品としては詩やカリグラフィーの台紙、本の装丁の装飾などに使われてきた。水の流線で作られ同じ模様がないことから、偽造を防ぐために公文書の用紙に使われた時代もある。現代の日本でも、平凡社ライブラリーという書籍シリーズの表紙に模様が使われている。

筆者(末澤)。背景は色鮮やかな「エブル」=トルコで
◆洋の東西をまたいだ「エブル」とは?
紙の文化とともに広がったエブルは、トルコ(当時はオスマン帝国)最大の都市イスタンブルで独特の発展を遂げた。単なる波模様だけではあきたらず、チューリップやバラなど、まちの人々が愛する草花を中心にさまざまなモチーフが作られるようになった。その美しさに惹かれたヨーロッパの人たちがエブルを「マーブリング(大理石模様)」と呼び、世界中に広めていく。一方、トルコ国内では、機械化の時代の波には逆らえず、手作業で作られるエブルは次第に廃れていく。だが、その技術を守り抜いた民族がいた。それがトルコ系少数民族のウズベク人だ。私は、15年前にエブルを現地で習い、彼らの末裔が住む丘を訪ねたことがある。末裔たちは、先祖がトルコの文化を守ったことを誇らしげに語っていた。
しかし、当時は、なぜウズベク人がエブルを守ろうとしたのかがよくわからなかった。絵本をつくる過程で、製本などの歴史を調べたところ、彼らがもともと住んでいたサマルカンドやブハラは、紙づくりで栄えた都市だった。彼らは、紙の製造技術に長けていたことから、紙製品であるエブルにも深く関わり、愛着や誇りを持っていたのだろう。オスマン帝国では、多数派とは平等ではないものの、異なる民族が、異なる特技を生かしながら暮らしていたという。そのあり方が垣間見えた瞬間でもあった。

「エブル」の制作風景=トルコで
『海峡のまちのハリル』の舞台としている100年前は、明治時代の日本人も世界を自分の目でみつめようと、イスタンブルを訪れたころだ。そこから、親日国として知られるトルコと日本の今に続く交流もはじまっている。
多様性とは、異なる人と人がであうことだ。これから、私たちはより多くの国の、より多くの人たちとともに生きていく時代を迎えることになる。その流れはコロナ禍があっても変わらないだろう。出会いの数だけ、私たちは新たな世界を広げ、つくり出していくことができる。この絵本は遠い時代の異国の話かもしれないが、今につながる何かがあると信じている。

『海峡のまちのハリル』(文・末澤寧史、絵・小林豊)
■参考URL
『海峡のまちのハリル』(文・末澤寧史、絵・小林豊、三輪舎刊)
トルコ文化センター