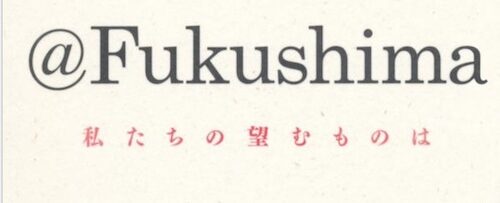2011年に出版した「希望」(旬報社)の紹介です。「まえがき」と「あとがき」を以下に掲載します。
https://amzn.to/3Evn5mD
*****************
◆はじめに◆
2005年の12月のことである。
その晩、遅くに戻った私は、部屋の中央にぶら下がった紐を引いて蛍光灯のスイッチを入れ、いつものように壁際のパソコンに電源を入れた。ジジジッという音を聞きながら、パソコンが立ち上がるのを待った。
単身赴任中だったとはいえ、1人暮らしの部屋はいかにも寒々としていた。畳の上に置いてある電気ストーブを引き寄せ、椅子の上に腰を下ろした。それも、いつも通りの所作だった。
パソコンのメール・ソフトを開くと、懐かしい名前が見えた。多数の広告メールの中に埋もれるように、彼の名前はあった。福島県に住む大学時代の友人である。実に久しぶりの、おそらくは十何年ぶりかの、彼の「肉声」だった。
大学卒業後、彼はいろいろな経験を経て、やがて山間部の郷里へ戻った。学生時代のある夏、私も一度、足を運んだことがある。山がすぐそこまで迫る、典型的な日本の田舎だった。そこへ戻った友人は、家業を継ぎ、家族を持ち、私や私たちと同様、日々の出来事に追われるような暮らしを続けていた。
◎ ◎ ◎
学生時代のある時期、私たちはほとんど毎日のように顔を合わせていた。彼はなかなかの好漢で、冗談好きで、明るく、穏やかで、モテた。有り体に言えば、ウマが合った。卒業後は連絡を取る頻度も次第に減り、やがて途絶えた。電子メールの前は、家族の写真入りの年賀状だったような記憶がある。にぎやかそうな顔と顔の間で、彼は学生時代の面影を十分に残して写っていた。
それから再び長い年月が過ぎ、世の中はいつの間にか、郵便から電子メールへの時代に移っていた。蛍光灯の下でメールを開くと、長年の無精を詫びる、ありきたりの挨拶に続いて、長くはない、しかし切々とした文章が続いていた。
◎ ◎ ◎
……こちらはと言えば、ひと言で言えば、家業の不振に喘ぎつつ、3人のこどもと妻、両親のために「死なない」で必死に戦っております。億の位の借金を抱え、体力の限り頑張っても、頑張っても頑張っても、なかなか事態の打開には至らないのが現実です。この状況で精神的にも鍛えられ、学生時代の自分はすっかり影をひそめてしまいました……。
君の「新聞とは何か?」という自問に負けず劣らず、「生きるとは、人生とは?」を毎日考えずにはいられません。「今までの人生、ほんとに甘かった。人に甘えて生きてきたんだな」と自分を責めたり、でも一方でそうは思えない自分もいます。
この1年、身近なところで3人も自ら命を絶ちました。その度に、自身の命も削られる思いです。あまりに過酷だと思います。普通の人間が普通に努力してるだけでは普通に生きられない社会。この現状に憤りと虚しさを覚えます。そういう意味でも、決して負けるわけにはいかないのです。もがいて、はいあがって、必ず事態を変えてみせます。「逃げない」ことが、こどもたちへの自分ができる最大のメッセージだと思っています……
◎ ◎ ◎
メールを受け取った約2カ月後、私は転勤のためロンドンへ移り住んだ。
スタッズ・ターケルの死去を知ったのは、英国生活が3年目に入った2008年11月か12月だったと思う。
ロンドンの冬は、実に寒い。ターケルの死を伝える新聞を読んだ日も本当に寒い1日で、友人のメールを読んだ晩と同様、体は芯から冷えた。
◎ ◎
ターケルは作家であり、ラジオの脚本家・パーソナリティーでもあった。しかし、彼を最も有名にしたのは、市井の人々の膨大なインタビューを集めた「良い戦争」や「アメリカの分裂」などの著作である。
私は学生時代からターケルのファンで、とくに「仕事!」を愛読した。邦訳は2段組で700ページ超もあり、115職種の133人が登場する。ターケルの死去を伝える英国のニュースが「Studs Terkel was the spokesman for millions of Americans」と表現したのも道理だと思う。名も無き人々の前にテープレコーダーを置き、ひたすら彼ら・彼女らの言葉を引き出す。それがターケルだった。
◎ ◎ ◎
私の仕事は新聞記者である。
ニュースを追うとき、記事の主語は、たいていが役所や組織、企業名、国の名であり、政治家や有名人である。あるときは「ロシアは」であり、別の時は「日本外務省は」だった。「自民党は」「厚生労働省は」「この裁判は」「警察は」……。記者になって25年、そんな原稿を山のように書いてきた。
そうしたニュースを扱いながら、一方ではいつも、何かが足りないような、ふらふらした感覚をぬぐえずにいた。そう、何かが足りない。「大地に根を張ったような感覚」欠落しているのだ。
記者になって10年ほどが過ぎたころ、ふだんなら決してニュースに登場することはない、市井の人々のインタビューを連載したことがある。要するに、ターケルの「仕事!」の真似である。
方言は方言のままで、口癖は口癖のままで紙面に載せる。人の話しぶりは、まさに、その生き方を反映していると思ったからだ。
温泉旅館の仲居、セールスマン、コンブ漁師、消防士、稲作農家…。「仕事!」の133人の密度とは比ぶべくもないが、それでも人々の息遣いは十二分に聞くことができたように思う。
例えば、路線バスの元運転手は私に向かって、こんな話をしてくれた。
彼は約20年間、北海道でバスに乗り、その前は長距離トラックの運転手だったという。文字通り、ハンドルこそが人生だった。
◎ ◎ ◎
……トラックにしてもバスにしても「事故を起こしたら」ってことが頭から離れなかった。私なんか2カ月に1回は夢を見てたね。バスに満員の乗客を乗せてね、あああ、ブレーキが利かない、あああ、ぶつかるぶつかる。その瞬間に目が覚める。そういう夢です。運転手なら同じような夢、みんな何度か見てますから。間違いなく見てるから。
トラック時代は、とにかく眠くてね。日中は小樽近辺で荷物を運び、夜8時から芦別、帯広行きの運転席に座る。着くのは翌朝でしょ。して、すぐ帰り荷を積んで小樽へ戻る。残業は毎月150時間から200時間。今と違って労働基準法とか関係ない世界さね。
体が丈夫だったから持ったけど、とにかく、すんごい睡魔なんだ。運転中は左手でハンドル持って、右手は髪の毛ひっつかんだり、足をつねったりで。あああ、と気が付いたら、反対側車線走ってたこともある。そういうことが2回あった。運がいかったんだ。紙一重だよ。あの時、対向車が来てたら、いまのおれはないもの。人生変わってたよ。
辞めたくなったこと? あるあるある。何度も。トラックの時もバスの時も。人間関係だ何だって、いろいろあるっしょ。バス会社を辞める時も、嫌な思いをした。でもね、今では何とも思ってない。恨みとか嫌な思いだけを抱えて生きていけないよ。
二女が生まれた時もね、なんも大変だとか思わなかった。7歳で亡くなったけど、あの子は生まれつき脳に障害があって、親の顔もわかんない、言葉も言えない。そういう子だったの。でも、とにかく、めんこい子でね。周囲からは「大変でしょう、大変でしょう」と言われたけど、何が大変なものか。普通の子供とおんなじですよ、私らにしたら。もう、めんこくて、めんこくて。
二女が生まれたのは、ちょうどバスが嫌で嫌でしょうがなかった時期だけど、「仕事がどうのこうの言ってる場合じゃない。おれが踏ん張らなきゃ」って、腹もすわった。ね? 親は子供のために頑張れるんだから。そうでしょ? 子供はかわいいに決まってるっしょ。嘆き悲しみなんて、ほんの一時のものでしょ?
◎ ◎ ◎
路線バス運転手の彼には夢があった。定年の日は自分で回数券を買い込み、乗客に手渡しながら、「きょうで私のハンドル人生は終わります、ありがとうございました」とアナウンスするのだ。しかし、定年の数日前、脳出血のため車庫で倒れてしまう。
「くやーしくて、悔しくて。あの悔しさ、一生忘れないよ」。過去に乗ったトラックとバスのナンバーを全部そらんじていた彼は、私の前でも本当に悔しそうに、そう繰り返した。
大手電機メーカーの猛烈営業マンだった男性から話を聞いたのは、彼が59歳の時だった。まさに、定年間際だった。
◎ ◎ ◎
……いつごろからですかねえ。50歳が見えてきたころかなあ。ぼんやりとね、考え始めてね。この先、どうなるんかいな、と。
私らの世代はね、だいたいが仕事一筋っていう生き方でしょ。私も完全な仕事人間でしたから。言葉としては嫌いだけども、戦士ですよ、企業戦士。営業マンとして働きずくめでした。いつも億単位の仕事やってましたよ。5億、6億は当たり前で。タクシー無線の設備とか、ビルの音響設備とか。地下鉄の構内放送設備、あれ、私らの仕事ですよ。
仕事への疑問? 持つはずないでしょ。ノルマはきつかったけど、本当に仕事が好きだったですから。どんな仕事であっても、ようし、おれがやったると。夜の付き合いも、とことんやった。40年近く、文句も言わずにね。もちろんお金も欲しかった。社内で評価もされたかった。社内表彰は何回も受けました。正直、それが内心、ずっと自慢でね。
それがですねえ、「この先どうなるんかいな」と考え始めると、いろんなことが浮かんできて…。一番は人間付き合いですよ。人脈を自慢したって、しょせん仕事の延長線でしょ。利害関係ですよ。そういう人は定年後、離れていくもんでしょう。仕事の垣根を越えた友人が、私にはいなかった。近所付き合いも女房任せだったし。20年も同じとこに住んでて、名字を言える家は何軒かしかない。地域のお祭りも行かなかった。ご近所さんとのバーベキューとかも、なかったです。休みの日、家へだれか呼ぶにしても、仕事関係の人しか思い浮かばない。
寂しいもんでしょ。そのことに、ある日ふっと気付いたんです。2人の息子も大きくなったし、このまま50、60、そして定年になっていいのかな、と。
そういう時、知人に韓国旅行に誘われたんです。海外なんて、恐ろしくて考えたこともなかったですけどね。第一、言葉が分からないでしょ。でも、その時は誘いに乗った。46歳だったかな。大げさに言えば、あれが分かれ目だったんだね、その後の人生の。
◎ ◎ ◎
団体の観光旅行だったが、そこで彼は「目覚めた」という。そして、何かにとりつかれたように、休暇を取っては海外旅行へ出るようになる。アジア全域、欧州、中東。やがて観光旅行では飽き足らなくなり、タイの貧しい村へ毎年2回、足を運ぶようになった。バンコクから車で8時間。ボランティア団体が主宰する旅である。
◎ ◎ ◎
……で、タイの奥地へ行ったらですねえ、想像を絶する世界があるわけですよ。本当に貧しくてね。子供たち、満足な食事もできないわけ。その瞬間、これだっ、と。ビビッときた。放っておけない、おれが何かやらなきゃいけない、って。仕事以外の興味、私はなかった。街頭の募金活動だって避けて歩いてた。その50男がですよ、突然、タイだ、ボランティアだ、と言い出すわけですから、周囲も最初は「どうしたんだ?」って。
タイ北部の山岳民族の村です。そこの子供たち、中学校へ行く資金がないんですね。その資金を「里親」として援助しながら、村の人々とも交流を深めるんです。寄宿舎を建てたり、校舎を建てたり。それと肥料の作り方ね、腐ったワラを混ぜるとか。豚の飼い方、野菜の作り方。そういう職業指導みたいなことをやって、子供はその作物や肉を売って学校の給食費にするわけ。
毎年2月と8月に2週間くらい会社を休み、ほかの仲間と一緒に行くでしょ。毎回、子供たち大歓迎でね。そりゃ、うれしいですよ。貧しいけど、純真なんですよ。本当に真っすぐなんだ。村は貧しいなりに、お互いが協力し合ってね。その雰囲気は、昔の日本と実に似てる。どこか懐かしい感じがして。
忘れられないことも多いです。初めてタイ奥地に行った時にね、地元の方々との自己紹介の場で「松下に勤めており…」と言ったら、村長が「自分は電器屋が一番嫌いだ。迷惑だ」と言い出して。「電気が村に通ったら、電器屋が電化製品を売りに来た。高過ぎて買えないと言うと、金貸しが来た。だから大勢の村人が金を借り買ってしまった。でも、金を返せない。そしたら結局、娘だ。娘をバンコクへ連れて行く。そういうことが、何回もあった。だから電器屋は嫌いだ」って。
何も言えなかったねえ。松下はタイへ電化製品を大量に輸出していた張本人だし、それに私らの常識では、電気は文化、文明の象徴じゃないですか。北海道だって、戦後しばらくは電気のない土地がたくさんあって、でも、電気が通れば常に感謝されたわけでしょ。私も「迷惑だ」なんて否定された経験ないですから。
忘れられないことをもう一つ。村の孤児院に行った時、子供たちが「自分の宝物をお土産に持って行って」と。で、何を差し出したと思います? 履き古したゴムぞうり。ぼろぼろのタイの漫画本。消しゴム、それも使い古しを半分に切ったやつ。ボロ切れもあった。泣けましたよ。私らは終戦後、ああいう体験してたわけですよね。それを忘れてたんですよね。
会社は57歳で退職しました。最後は営業の課長職で、その後、再就職し、さらに今は別の会社に勤めています。私は恵まれてましたね。松下時代は、タイ行きの長期休暇も何も言わず取らせてくれた。それを当たり前のように感じてたんですが、でも世の中、そうじゃないですよね。ボランティアしたくたって、休めない環境の人もいる。その方が多いわけでしょ。大会社に勤めてる人は、だいたいがその待遇を世間一般の相場と思い込み、自分がいかに恵まれているかを忘れてるんじゃないですか。少なくとも、私はそうだった気がするんですね。
ずいぶん昔、高校卒業の時ですけど、私、おやじの勧めで警察官の試験を受け、合格したんです。おやじも刑事でね。けど、土壇場で警官になるのをやめた。で、おやじに詰め寄られた時、言ったんです。「父さん、いつも家にいなかっただろ。将来結婚したら、女房、子供にこんな寂しい思いをさせたくない」って。そしたら、おやじ、ボロボロ泣いたですよ。私の前で初めて泣いた。「おれ、そんなに寂しい思いさせてたんか」って。
そんなことがあったのに、私も家族をほったらかして、仕事人間になってたわけですよね。進む道は一本しか見えなかった。本当に仕事、仕事、仕事で…。仕事人間だったことを後悔しているわけじゃありません。会社に恨みを持っているわけでもない。それどころか、好きなことさせてもらって、感謝してます。仕事は本当に好きだった。
いま、夢があるんですよ。足腰が立たなくなるまで、タイの困っている人に力を貸したい。ベトナムやカンボジアでも役に立ちたい。もっと世界が見たいんです。現役バリバリのころは、夢なんて、考えもしませんでしたけどね。
◎ ◎ ◎
路線バスの元運転手も、猛烈営業マンだった彼も、そして、ほかの大勢の人たちも、当たり前のことだが、だれもがみな、懸命に生きていた。小さな誇りや生き甲斐や喜怒哀楽を織り交ぜながら、それそれが懸命に。スタッズ・ターケルの「仕事!」に登場する人々も、それは同じだ。
「仕事!」の中で、レンガ積み職人は「自分が積んだレンガの塀は、今でもすべて思い出せる。若い時の仕事の前を通ると、全部崩してやり直したくなるんだ」と言う。
人々の日々の仕事は単調で退屈で、もちろんニュースにもならない。でも、私はそこにひかれるようになった。ふつうの人々が織り成す、ふつうの日々。時に見失いがちな「希望」も含め、社会と時代のすべてはそこにある。その考えは、間違っているだろうか。
◎ ◎ ◎
十二分の時間をかけて、それぞれの人々が心の奥底に抱える生き様に耳を傾け、それを多くの人に届けてみたい--。この本は、そんな着想が基礎になっている。
本書に登場する64人は、性別も年齢も職業もばらばらだ。あらかじめ、何か決まったカテゴリーがあったわけでもない。有名人もいる。社会や地域の一定の範囲でこそ著名な人もいる。それこそ、全く無名の人もいる。
登場人物だけでなく、聞き手(書き手)もばらばらだ。著名なライターもいれば、無名の人もいる。
唯一のつながりがあるとすれば、それは、聞き手(書き手)が筆者の知人か、知人の知人だった、という点だけである。
本書の構想が最初に持ち上がった2010年の春先、私は電子メール・ソフトのアドレス帳を開き、そこから知人たちに向け、こんな電子メールを一斉送信した。メールは知人から知人へと転送され、多くの方から返事が届いた。
◎ ◎ ◎
……なんだか、パッとしない日々が続いています。新聞やテレビに目を向けても、重苦しいニュースや暗い話題ばかりが目に付きます。貧困、格差拡大、不況、低賃金、自殺、就職難、借金苦、失業増加…。いったい、こんな活字やこれに類する映像をどれほど見てきたことでしょうか。
都会は都会で、地方は地方で、田舎は田舎で、それぞれがそれぞれに、「先行きが見えない時代」に覆い尽くされているようにも思えます。少し前、私が郷里・高知市に帰省した折は、あれほど賑やかだった中心部の商店街が、ものの見事に寂れ、何とも言いようのない気持ちになってしまいました。でも、一方では、「そうじゃない」「暗いばかりじゃない」という、当たり前のことも感じます。
この広い日本では、実は、われわれの目の届かない場所で、地べたに足をつけて、踏ん張って、そして希望を持ちながら明日への道を切り開いている人々も大勢します。有名かどうか、成功しているかどうか。そういったことに関わりなく、何かを信じて、どこかに展望を持って、日々格闘している。そういう人々が間違いなくいるはずです。
そんな話を過日、東京の出版社の方々と話していたところ、それを活字にできないか、そうした人々の声を集めて1冊の本ができないか、その結果、少しでも多くの人に希望と勇気をお裾分けできないか、ということになりました。
テーマは「希望」です。
北海道から沖縄まで。都会も田舎も海辺も山間部も。若い人も年配の人も。おそらく、それぞれの場所でそれぞれの人がそれぞれの方法で、「希望」を見出し、この社会を少しでも良くしよう、少しでも良い明日を迎えようと、頑張っているはずです。その肉声を集め、そして、今の日本に「希望を信じて歩む人たち」の声を送り出し、ほんの少しでも(実際にほんの少しでしょうが)明日を信じることができるような社会にするために、微力を尽くしてみたいと考えています……
◎ ◎ ◎
冒頭で紹介した、福島県に住む友人からの電子メールは私のパソコンにずっと保存されている。その最後は「……ありきたりですが、ばらばらにされた一人一人を結ぶ大きな仕事を君の力でぜひ実現してください。期待しています」という文章で結ばれている。
その言葉の意味を今も時々考える。
どんなにしんどいことがあっても、楽しい日々が続いていても、あるいは、立ち止まる余裕を無くしていても、時間だけは確実に進む。私も他の誰も、自らの歩みを止めることはできない。足を前に出すことは止められない。進んでいる方角が分からなくても、隣にだれがいるのかを見失っていても、希望を見つけることが困難になっているとしても、だ。
だから、「希望」と「つなぐ」には意味がある。少なくとも、この本の聞き手たちはそう考えているし、あなたにもそれを感じ取ってもらいたい。そう願っている。
2011年初夏
*****************
◆「希望」のあとがき◆
2011年3月11日に東日本大震災が発生したとき、ちょうど、この本の校正作業は最終盤に差し掛かっていた。多くの人と同様、私もその後しばらくは、呆然とした日々を過ごしていた。日常と変わらぬ生活を送っているつもりでも、心ここにあらずだった。
このあとがきを書いている5月20日の時点で、亡くなった方、行方不明の方は2万人を軽く超えている。実感することが難しい数字ではあるが、おそらくは、一つの地震で2万人超の方々が犠牲になったと考えるよりも、犠牲者が1人出た地震が2万件超に上ったという捉え方が正しいのだと思う。
例えば、本書の遠藤明子さんの話にも出てくる、宮城県石巻市の大川小学校。この小学校では地震直後、教員の誘導で集団避難を試みたものの、全校児童108人のうち7割が津波の犠牲になった。教員にも多数の犠牲者が出ている。震災から40日余りがたった4月末、大川小学校は別の学校を借りて卒業式を開いた。当時の6年生21人のうち、無事が確認されているのは、5人だけ。卒業式では、死亡・行方不明児童の親族も大勢集まったという。
その様子を伝えるニュースを私は涙なしには読めなかった。
式では、校長先生が「ご家族に何とか証書を渡すことができた。このような悲しいことが起きないように職員でがんばっていく」と話し、長女を失った父親は「おめでとうといってあげたい。区切りとして卒業式に参加した」と目を赤く腫らした。子供2人を亡くした母親は、仕事の合間に不明者捜索を手伝っているという。「自分の中の時間はあの日で止まっている。自分たちがなんで子どもを迎えに行かなかったのか、今まで考えてきたし、この先もずっと考え続けると思う」(朝日新聞2011年4月24日夕刊)
同じような話は、それこそ枚挙に暇がないほど伝わってきた。歩みの遅い老人を横目に高台に逃げ、自分をずっと責め続ける人がいる。津波に翻弄される中、肉親の手を離してしまい、「もう立ち直れない」と悔いる人がいる。自分や親族は無事であったとしても、漁船を失い、家財道具を失い、家を失い、田畑を失い、大事な思い出を失い…。そうした大きな喪失感の中で立ち竦むしかない大勢の人々がいる。
テレビや新聞を通じて、「頑張ろう」という掛け声が溢れても、当事者はそんなに簡単に前を向けるはずもない。それもまた自明のことだろうと思う。
「希望」に関する本をつくりたいと思ったのは、2010年の年春ごろである。東日本大震災が起きる、ちょうど1年ほど前のことだ。私は自分の思いを数枚のペーパーにまとめ、知人に送り、知人はさらに知人に送り、それが繰り返される中でインタビュアーの顔ぶれがそろっていった。
私自身は、新聞記者になって20年以上になる。相も変わらず日々のニュースを追いかけながら、しかし、ここ数年は「なにか違う」という思いを払拭できずにいた。
当たり前の話だが、世の中は新聞やテレビのニュースが伝えるような、「日本政府は」「日本経済は」「○○事件は」といった大文字の世界で動いているわけではない。都会は都会で、地方は地方で、田舎は田舎で、つまりは自分たちの目がなかなか行き届かない場所で、地べたに足をつけて、踏ん張って、そして希望を持ちながら明日への道を切り開いている人々が大勢いる。有名かどうか、成功者かどうか。そんなことにはかかわりなく、何かを信じて、信じようとして、どこかに展望を持って、日々格闘している。そういった人々こそが、世界の中心であるはずだ-。
そんな思いが消えなかったのである。
スタッズ・ターケルという稀代のインタビュアーが米国にいた。2008年11月に96歳で死去するまで、「よい戦争」「仕事!」「アメリカの分裂」といった名著を数多く残している。ターケルは録音機を駆使し、テープを回しながら、いつも市井の人々の声に耳を傾け、言葉を引き出した。数々の著作を読むと、彼の死去に際して英国のBBCが「Studs Terkel was the spokesman for millions of Americans」(スタッズ・ターケルは無数のアメリカ人の代弁者だった)と報じたのも道理だと思えてくる。
だから、この本をつくるに当たっては、そのターケルの手法に寄り添って、人々が語る言葉にひたすら耳を傾けたいと考えていた。同時に、本書の趣旨が人から人へと伝わる中でインタビュアーが集まったように、ばらばらだったものを「つなぐ」ことを、何より大切にしたいとも考えていた。それらはおそらく、情報の多くが「東京から地方へ」「中央から末端へ」と流れる中で、どこか歪んでしまったこの情報化社会に抗う、数少ない有効な手段だろうと感じている。
東日本大震災が発生した後、本書は締め切りを延ばし、震災関連で5人の方を追加した。それぞれの人々言葉を、それぞれが語る「希望」をどう読み取るかは、読者の方々にお任せするしかない。大川小学校児童の母親が言った「自分の中の時間はあの日で止まっている」という言葉の前では、「希望」もかすむかもしれない。
でも、編者として本書に登場する人々の言葉の記録を熟読した私には、ぼんやりと、でも確かに思うことがある。どんなにささやかであっても、どんなに泥にまみれていても、そして目の前から消え去ったように感じても、そう簡単に「希望」はなくならないのではないか、と。
むろん、「希望」は、キャッチフレーズのように、漢字2文字だけで語られるべきものではない。この単語を繰り返したところで、何も伝わりはしない。なぜなら、「希望」は、それぞれの人が積み重ねてきた長い長い時間の中に、あるいは、これから積み重ねる長い長い時間の中に、目立たない形で潜んでいるに違いないからだ。
「まえがき」で記した福島の友人には、震災後、長期の無沙汰を詫びつつ、現地の様子をうかがうメールを送った。その返事がなかなか来ない。じれったくなって、5月のある月曜日の午前中、彼の会社に電話してみた。従業員の「はい、代わります」という声のあと、懐かしい、本物の「肉声」が受話器から聞こえてきた。
「お、どうした? この前のメール? 読んでるよ。ちゃんと読んでるって。きちんと返事書こうと思っているうちに遅くなっただけださ。なんとかやってる。元気に決まってる。当たり前だろ、そんなの。それよりさ、週初めのこの時間帯、忙しいんだよな」
おまえの相手なんかしている暇はないんだよ、と言わんばかりの早口。遠慮のないその声が、この上なく、うれしかった。
2011年初夏