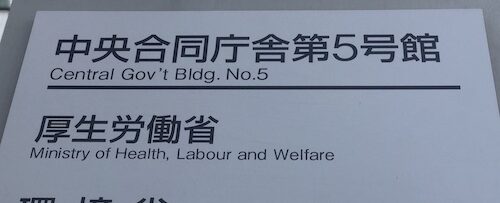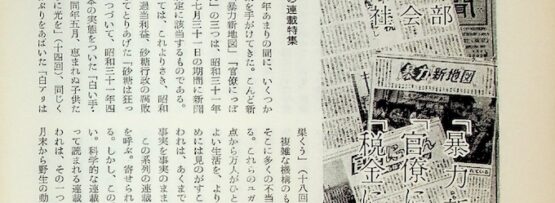読売新聞大阪社会部(1984年)
[ 調査報道アーカイブス No.63 ]
◆拘置所から届いた便せん7枚「僕たちは無罪だ」
著名な冤罪事件や再審事件であれば、重厚な弁護団が編成されて、世間やメディアからも注目される。だが、無名の被告人であっても、冤罪の苦しみは変わるものではない。
今から40年ほど前、そうした冤罪事件が大阪であった。
1984年4月17日。読売新聞大阪社会部の司法記者クラブの担当記者に1通の封書が届いた。差出人の住所は大阪拘置所。「拝啓、突然のお手紙で失礼致します」で始まる便せん7枚の手紙は、1979年1月21日夜に大阪府内で起きた女性(27)に対する暴行・殺人事件の加害者からだった。
この事件には、5人の“犯人”がいた。事件当時21歳だった男性、および18歳だった少年4人である。すでに一審で懲役刑に処せられていた。手紙の主はそのうちの1人である。
便せんには、自分たちは無実であるとして次のような内容が記されていた。少年の1人は知的障がい者であり、被害女性の夫から暴力で脅されて「殺したのはボク達です」「仲間は●●です」と紙に書いてしまったこと。警察はそれを信じてしまったこと。警察では毎日殴られ蹴られ、その恐怖から逃れたい一心で虚偽の自供調書に指印してしまったこと。血液型の鑑定がおかしいこと……。
◆冤罪の訴えには“偽り”も少なくないが……
冤罪を訴えるこうした手紙が獄中や拘置所から新聞社に届くのは珍しいことではない。裏付け取材をすると、すぐに偽りだと分かってしまうものが大半だ。この事件はどうだったか。読売新聞の記者が他紙を含めて過去記事を調べてみると、報道内容に冤罪を思わせるものはない。5人の不良グループに対し、一審大阪地裁は殺人などの罪で懲役10~18年を言い渡している。便せん7枚の訴えとは、落差が大きすぎる。この手紙も偽りか…。しかし、司法担当の記者3人はそう思えなかった。「これまでの手紙とはちょっと違う」。何かひっかかりを感じたのである。
記者たちはその後、どうしたのか。取材のプロセスをも記した『逆転無罪 少年はなぜ罪に陥れられたか』などを紐解きながら、その経過をたどってみよう。

イメージ写真
◆食い違う血液型、供述内容もばらばら。しかし一審は有罪
この事件の一審で被告・弁護側は「物証」「自白の任意性」「アリバイ」の3点から無罪を主張していた。記者3人は公判記録を読み込み、ポイントを把握していく。
「物証」とは、血液に関するものだ。遺体から検出された血液反応はA型で、被害者の女性もA型だった。一方、被告5人の中にA型は1人。しかし、体液から血液反応が出ない非分泌型である。残り4人のうち2人はB型、2人はAB型だ。検察側は「5人が次々に被害者を強姦した後、殺害した」と主張していたが、なぜB型の血液反応が出なかったのか。「それは5人が無実だからだ」と弁護側は主張していた。
「自白の任意性」については、共謀した時刻や場所、強姦の順番や方法をめぐって5人の自供の内容は食い違いが激しいとして、弁護側は「供述調書の信用性は乏しい」と訴えた。「アリバイ」については、被告側に有利なアリバイを証言した複数の男性に対し、警察が脅しや暴力を振るい、被告に不利な証言を強いたと主張していた。
裁判所はそうした弁護側の主張を退け、ほぼ求刑通りの判決を下している。拘置所からの手紙に心を動かされたものの、記者たちは迷った。「冤罪か否かは不明なのに、どれだけの力を入れて取材すべきか」。そんな迷いを抱えたのも当然だった。
1
2