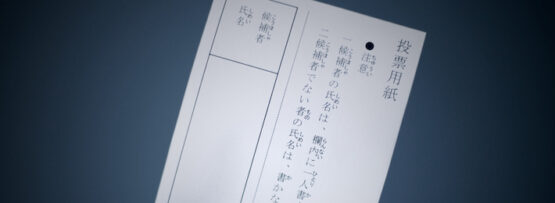「木村王国の崩壊」朝日新聞福島支局 吉田慎一記者(1976年〜)
[ 調査報道アーカイブス No.10 ]
「木村王国の崩壊」は、地方権力の暗部をえぐり出した、古典的な調査報道だ。
1976年(昭和51年)の春から夏にかけ、中央政界を揺るがせたロッキード事件と並行するように福島県政汚職事件は進行していた。きっかけは、県南部の天栄村で起きた水道管敷設工事をめぐる贈収賄事件。この事件の贈賄業者を福島地検が取り調べる中で、事件の舞台は県庁へと飛び火する。営繕課長は県警が逮捕し、総務部長については福島地検が独自捜査で逮捕した。
福島地検のターゲットはこの年の4月に4期目の当選を圧倒的票差で成し遂げたばかりの木村守江・福島県知事に据えられた。知事後援会の最高幹部である自民党県連幹事長、農協五連会長。地検はまず、この2人を公職選挙法違反(特定寄付の禁止)で逮捕し、最後は木村知事を収賄容疑で逮捕した。木村知事は当時、全国知事会会長を務める実力者。県政ぐるみの一大汚職事件に発展したこの一連の捜査は、「福島のロッキード事件」とも言われた。
この事件に関し、朝日新聞福島支局は「福島県総務部長を取り調べ」と「木村福島県知事取り調べへ 数百万円を収賄」という記事をスクープした。しかし、それが評価の対象ではない。特筆すべきは木村知事の起訴後、捜査が一段落したときに福島県版で始まった「木村王国の崩壊」という長期連載企画だ。スタートは1976年8月。当初は100回程度の予定だったが、最終的には翌77年12月まで235回も続いた。担当記者は、入社3年目だった吉田慎一氏。連載の内容については、同氏の著書「ドキュメント自治体汚職 福島・木村王国の崩壊」(朝日選書)などに詳しい。
この長期連載そのものは、隠れた疑惑や不正を明るみにしたわけではない。だが、圧倒的なディテールの迫力で読む者を放さない。
贈収賄とはどんな犯罪なのか。業者側のどんな思惑からわいろとして現金が贈られ、収賄側の知事や県職員らはどのような心境で受け取ったのか。収賄側は事情聴取の際は何を考えていたのか。捜査する側はどのような手順で被疑者を追い詰めていったのか。逮捕後に留置所(拘置所)では何を考えていたのか……。そういった事柄について、これほど事実を丹念に積み上げて描いた記事はおそらく前例がない。
連載のある回は、贈賄業者の立場で。別の回は被疑者である県庁幹部の立場で。また別の回は検察官、検察事務官らの立場で。その時々の心の動きまでもが丁寧に記述されている。取調室でのやり取りなどは、検察官と被疑者それぞれの息遣いまで伝わってくる。伝聞や半ば想像で書かれたのならそれはフィクションに過ぎないが、すべてが当事者に丹念に取材を重ねたファクトで構成されている。
1990年代半ば、贈収賄事件を担当する北海道警察捜査2課の次席は、警察担当の新聞記者だった筆者に対し、「『木村王国の崩壊』は、サンズイ(汚職事件)の仕組みや全体像を細かに描いている。サイズイを挙げることが仕事の自分たちにとって、教科書のような書籍」と話していたものだ。
細部へのこだわりは、まだある。
一連の事件を指揮した福島地検の検事正が着任する際の記述では、上野発福島着の特急列車が定刻より何分遅れ、検事正はどのようなポーズでホームに降り立ったのかといった事実にもこだわった。
被疑者は福島地検のどの建物のどの部屋で取り調べを受け、机をはさんでどの椅子に座ったのか。取り調べ中に被疑者はお茶を何杯飲んだのか。知事公舎での現金授受の際、業者は応接室のソファのどこに座り、知事はどこに座ったのか。現金入りの封筒は風呂敷で包まれていたのか、封筒は何色だったのか。こうしたディテールについて、一つたりとも揺るがせにしていない。だから読み手は、事件に関係するすべての場面について文字を追うだけで映像化できるのだ。
先輩記者の助言を受け、吉田記者はドキュメントに迫真性を出すことに力を注ぐ。そのため、「……という」「……といわれている」といった伝聞形式の表現をことごとく排除した。著書の「あとがき」で吉田氏はこう書いている。
「連載開始当時、私の手元には夜回りなどの取材ノートが8冊たまっており、使える情報がたくさんあるつもりだった。しかし、いざドキュメントとして事柄の正確さを期そうとすると、ノートに記された話は単なる取材の端緒に過ぎなかった。すべてが再取材、再々取材を必要とした。私自身が体験しない状況を『……であった』という直接表現で書く以上、当事者本人、少なくともその場に直接居合わせた人の話を取材しなければならなかった。それは予想以上に大変だった」
取材して人から聞いた話では、その真偽が常に問題となり、同じ場面で2つの相反する話が出ることもあった。1つの断定文を書くために1日近く費やすこともあった。取材を進める中では、すでに裁判で確定した「事実」が事実ではないと確信したこともあったという。
「スピードを要求される日々の報道では、ともすれば『……という』式の伝聞スタイルに寄りかかりがちになる」とした吉田氏は、こうも記している。 「伝聞スタイルの持つ安易さが、真実をねじまげることはなかったか―。自らの報道姿勢を反省させられることも多かった」