◆取材はそもそも暴力性や恥と背中合わせだ 「あなたにその自覚はあるか?」
辺見氏は「もの食う人びと」に、ソウルの日本大使館前で割腹自殺を図った元従軍慰安婦の女性とのやりとりを、取材過程とともに記している。(太字斜体は高宗。ネンミョンは冷麺のこと)
「使ったサック(コンドーム)をね、将校が来る前に洗うのよ」
金さんは両の親指と人さし指でゴムを摘(つま)む動作をしてみせた。
「小川でね。みんなしてね、しゃがんでね。辛かったですよ、情けなかったですよ、これがいちばん」
私のネンミョンはゴムひものように硬く喉(のど)をふさいでいる。
あの、そのサック洗いの時、月がですね、その、満月とかが出てなかったですか。かすれ声で問う。私の描いた情景に、月はあった。川面に映り、揺れていた。たぶん、あとでそう書きたかっただけなのだ。
金さんは答える。
「なかったです。いつも曇っていたですよ。一度に四十個も洗ったりしたですよ」
あんた、あれがね、サック洗いね、忘れられないよ。いまでもね、思い出がやってくるのよ。いつか日本に行って、私死ぬところを、日本人に見せつけてやりたくなるのよ……。
私は金さんを半世紀前の記憶の古井戸に突き落としていた。
取材する側としては、どんなに辛い経験でも従軍慰安婦としての経験に触れざるをえない。記者という職についている人の多くは、この点に納得すると思う。一方、満月について聞いた過程を記す記者がどれだけいるだろうか。あえて記さなくても、原稿は成り立つだろう。原稿の流れからすれば余分なものと考え、私なら割愛すると思う。少なくとも、書き手の想定通り「満月があった」と女性に言わせようとしたことを、気まずく思い、そのやりとり自体をなかったことにしようという心理的な防衛機制が、間違いなく働く。
女性のエピソードをメインととらえたときに、背景に退いているこの余計な部分にこそ、辺見氏は取材者の特権的な立ち位置を暴露させているのではないか。「書く側だけ無傷ではいられない」とでも言うように。女性を半世紀前の記憶の古井戸に突き落としてでも旧日本軍の蛮行を暴く行為を、厚顔無恥に転落することから踏みとどまらせているのは、この自己批判だと思う。
所属しているマスコミの大小によらず、記者クラブに所属しているかどうかによらず、取材という行為がそもそも暴力性や恥と背中合わせだ。背中から噴き出した油汗に、私はこう確信している。取材や調査報道の力は、もちろん権力者と対峙(たいじ)したり、社会的な問題を暴露したりすることに使わなければいけない。しかし、さらに言えば、「もの食う人びと」が教えてくれているのは、取材者がその暴力性への自覚を失い、きれい事で塗り固めた途端、報道が総崩れするということだ。
辺見氏の視線が問い掛けてくる。「あなたは自覚があるか」と。
取材者は見る側ではない。見られる側だ。
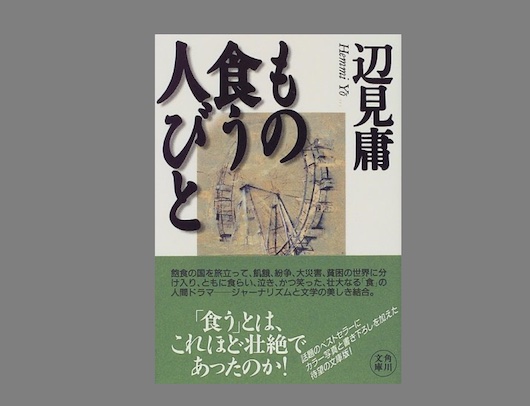
「もの食う人びと」
■参考URL
「もの食うの人びと」(辺見庸著)=角川文庫版・初版1997年
「1★9★3★7(イクミナ)」(辺見庸著)
辺見庸ブログ
2







