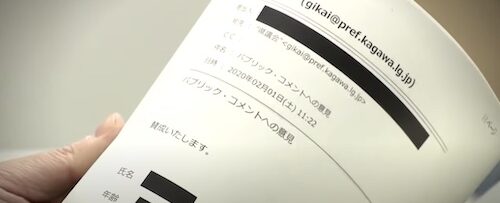◆時に冤罪にも加担する報道 それでいいのか?
それまでのマスコミは長く、「容疑者=犯人」という図式の報道を続けてきた。どんな容疑者であれ、裁判で判決が確定するまでは「推定無罪」が適用されるという原則を忘れ、大きな事件になると、容疑者の“悪者ぶり”を集中して報じた。その傾向は今も変わっていない。警察からの情報を鵜呑みにし、そこに寄りかかって報道を続け、時には冤罪にも加担していく。そんな事件報道の在り方を放置したままで良いのか。
西日本新聞の取り組みに関わった当時の社会部・寺﨑一雄氏は2020年7月の同紙にこう書いている。
「当事者双方から話を聞く。それが取材の鉄則だが、容疑者が警察に身柄を拘束される犯罪報道では不可能となる。そこから、警察情報をうのみにする構図が生まれ、時には「罪(えんざい)」報道にもつながるのではないか。
逮捕は本来、捜査の手続きにしかすぎない。さらに法の理念は「無罪の推定」にあり、どんな容疑者であれ、有罪判決が確定するまでは無罪と推定される。しかし、一般には「逮捕=有罪」という印象が鮮烈であり、後に無罪が証明されても名誉回復が容易でない。
そんな中、警察が公判維持に有利な「クロ」の材料ばかり提供し、捜査当局に不利な部分を隠したとする。こうした情報操作に対し、私たちは対抗する術(すべ)がほとんどなかった。当事者である容疑者から話を聞いて、反証を挙げるといった作業ができなかったからである。
かねて一方通行的な回路に風穴を開けたかったのだと寺﨑氏は言う。警察からだけでなく、容疑者の言い分も聞きながら、事実を多面的に積み上げていくのだ、と。しかし、警察や検察からは当然、猛反発を招いた。「西日本が敵に回った」として、広報担当以外は取材に応じない警察署が相次いだ。「言い分」とはいえ、自分の名前が何度も紙面に出ることで、容疑者自身が「苦痛」を感じたという報告もあった。読者からは「警察につかまるような悪に手を貸すのか」という意見も届いた。
それでも、西日本新聞の取材班は「実験」をやめなかった。「事件と人権」に関する連載キャンペーンも絡めながら、1年余りの「実験」を続けていく。その中には、暴走していないのに暴走したとして逮捕された少年の事件もあった。“誘導尋問で自供を強いられた”との言い分だ。この事件は結局、西日本新聞の調査報道取材も手伝って、少年は罪に問われることはなかった。冤罪を防ぐという成果も生み出したのである。
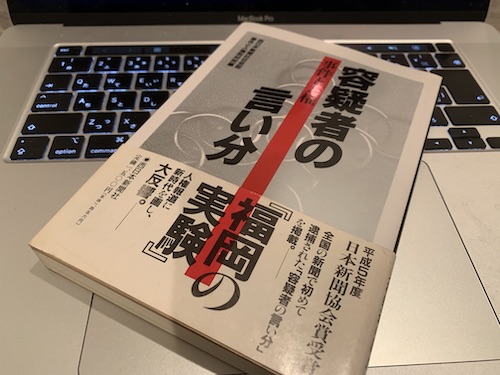
■参考URL
単行本『容疑者の言い分 事件と人権』(西日本新聞社会部編)
2