『大切に保管している100枚ほどの「下書き」がある。
「私達は元気だった娘を返して欲しい」
パソコンで打ち込まれた長文に、赤ペンでいくつも書き込みがされている。』
こんな書き出しで始まる記事が2022年1月18日、中日新聞WEBで公開された。『被害者取材、このままでいいの? 現場から逃げ出した私が考えたこと』というタイトルで、筆者は秦野ひなた記者だ。
事件事故の現場や被害者遺族らのもとに足を運ぶ取材は、新人でなくてもつらい。追い払われ、罵声を浴びることも珍しくない。記者の多くは「こんな取材に意味があるのか」という自問を繰り返し、足は止まる。秦野記者もそんな1人だった。
取材を始めて3年目で多治見支局にいた私は、それまでにも何度か被害者への取材に携わっていた。
大勢の他社の記者とともに被害者の自宅前で夜な夜な遺族を待ったことも、大切な人を亡くしてぼうぜんとしている人に頼んで、故人の免許証の顔写真を撮らせてもらったこともある。
事実を記録し、被害者の生前の姿を読者に伝えることも、事件や事故の再発を防ぐための大切な仕事のひとつだと言い聞かせ、なんとか自分を保った。一方で「もし私だったら、絶対にされたくないことをした」という罪悪感に押しつぶされそうだった。
◆「誰かを傷つけるかもしれない。そう考えると眠れなくなる」
秦野記者は岐阜県の多治見支局員だった当時、ある交通事故を取材する。20歳の女性が、スマートフォンに気を取られた車にはねられ、亡くなった。遺族となった父母に会った際、父親から「下書き」を手渡された。それが冒頭に出てくる「下書き」である。父親は刑事裁判で使うつもりだったという。しかし、秦野記者はうまく記事にできないまま、時を重ねていた。
その後も、担当地域では何度も事件や事故が起こり、その都度、被害者の取材に携わった。明日もし担当地域で何か起きたら、また誰かを傷つけるかもしれない仕事が待っている ― そう考えると眠れなくなった。
数年後、私は取材部門を離れた。
現場には、真摯に被害者と向き合い、大切なメッセージを伝え続けている記者がたくさんいる。そうなることも、そのための努力も工夫もできなかった。ただ現場を逃げ出した自分が情けなくて、竹田さんとの連絡も途絶えがちになっていた。
そんなとき、「生命(いのち)のメセージ展」が多治見市に巡回してくることになった。それが昨年秋のことだった。
「ひとみが、多治見に遊びに来ます。都合がつけば会いに来てください」
昨年10月下旬、吉弘さんからの、久しぶりの連絡。これに応えなかったら、もう二度とこの問題と向き合うきっかけを掴めないかもしれない。

「生命(いのち)のメッセージ展」の様子=YouTubeの公式動画から
思いもよらぬ出来事で犠牲になった人やその遺族たち。そうした方々の思いをどんな形でどう伝えるのか。事件事故取材への批判は止まないが、実際に現場で動いている記者はどんな思いを抱えているのか。記者のそんな揺れる心が、この記事からは見えてくる。
◆「生命のメッセージ展」と取材
「生命(いのち)のメッセージ展」そのものは、2001年3月に初めて開かれた。誰がどのようにして始めたのか。そのいきさつはNHKの木原恵記者の記事『「生きてこそよ」 ~記者の背中を押した生命のメッセージ』(NHK事件記者/取材note 2021年7月30日)に詳しい。この展示会を始めた鈴木共子さんはかつて、大学生になったばかりの息子を交通事故で亡くした。その後の日々は筆舌に尽くし難く、記事を読みながら落涙しそうになる。
秦野記者と木原記者の記事を読んでいくと、「被害者にも伝えたいことがある」という当然のことが見えてくる。突然の事故で身内を失った遺族たちの、重い叫び。それをすくい取って社会に広げていく営みは、“被害者に寄り添う”といった手垢のついた言葉では表現しきれない。そんな難しい問題に、各地の記者たちは挑んでいるのだ。
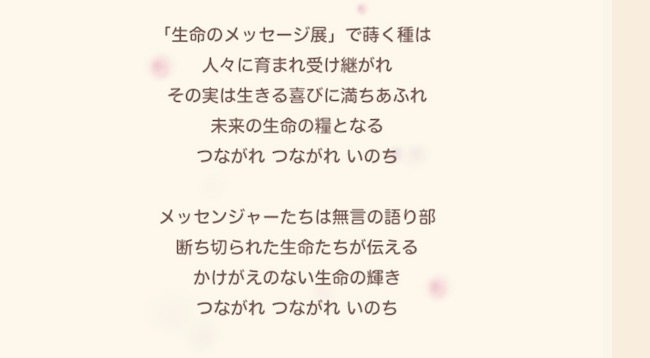
「生命(いのち)のメッセージ展」のHPから
■参考
『被害者取材、このままでいいの? 現場から逃げ出した私が考えたこと』(秦野ひなた記者 中日新聞WEB 2022年1月18日)
『「生きてこそよ」 ~記者の背中を押した生命のメッセージ』(木原恵記者 NHK事件記者/取材note 2021年7月30日)
「生命(いのち)のメッセージ展」公式サイト
『小さな命を救え! CDRという壮大なチャレンジ』(フロントラインプレス)

