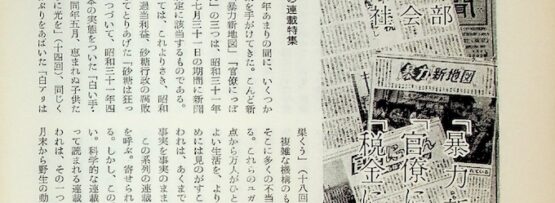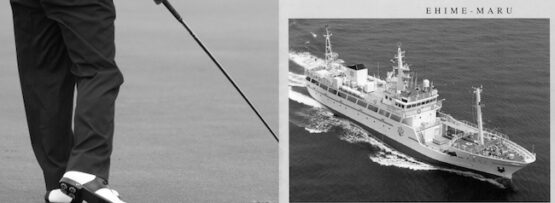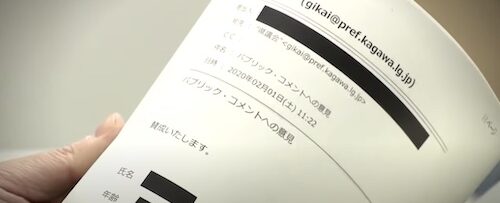「500人の村がゆく」 高知新聞 (2007年)
[ 調査報道アーカイブス No.28 ]
高知県の大川村は四国山地の只中にある。どこまで行っても山、山、山。人口減少と高齢化から村議会議員のなり手がいなくなり、2017年に「議会廃止」を検討したことがある。定数は6。その数の立候補者すら確保できそうになく、地方自治法に則って議会の代わりに「町村総会」を置こうと考えた。このこと自体は当時全国ニュースになったため、記憶している人もいるかもしれない。
コンビニも飲み屋もない。商店は雑貨屋などが1、2軒。当時の人口は約400人だが、それより10年前の人口は約500人だった。10年で100人減った計算である。
いったい、この村はどうなるのか。「限界集落」とか「消滅自治体」とか、そんな呼称で十把一絡げにされる各地の集落では何が起きているのか。鋭い観察力をもってそれに迫ったルポが「500人の村がゆく」である。2006年1月1日〜6月14日、高知新聞で連載された。初回はこう始まる。
なんという遠さだ。土佐郡大川村下切の一軒家に地図を手に出向いたのは、マムシうごめく初夏だった。
県道脇に車をとめ、水力発電所の取水口そばから分け入る。最初は、ズッコケたように全体が傾いた階段。さらに進むと、下手の森から上がってくる運搬用モノレールの心細い軌道と合流する。黒白の猫が一匹、とぼけた顔でレールに座っていた。
石と土の急な坂道を上り切ると、今度はなだらかな草むらだ。足元を見ると、赤マムシがとぐろを巻き、毒々しい鎖模様を動かしている。
絶叫して跳びはね跳びはねしているところへ、今度はスズメバチの羽音が首筋にぶーんと来た。また絶叫。後で聞いたら大形のアブだった。飛行訓練中の軍用機が二機、ごう音を響かせて上空を飛び去った。
大川村は、車の入れない山中に、まだぽつぽつ家がある。

過疎の現状を伝える同紙の記事については、調査報道アーカイブスのNo.2でも取り上げた。「高齢化」「地域の衰退」という点から見れば、高知県はかなりの“先進地”だから、地域密着の地元紙はそれに鋭く迫ることができる。
「500人の村がゆく」を取材するため、高知新聞記者は大川村に1年近く住み、無給の研修員として役場で働いた。無給の研修員という身分だが、事業課に籍を置き、仕事机ももらった。村に住み、村で働き、コミュニティーの一端を担ってこそ見える風景がある、そう考えたのだ。連載はその記録である。取材した石井研記者は書いている。
高知県大川村は人口五百九人(2006年11月30日時点)。離島を除いて人口最少の自治体だ。小さくて、広くて、遠くて…。東京を日本の極とすると、対極がこの村ではないだろうか。カネの潤沢さ、若い活力という東京の光がこの村では影となり、犯罪、息苦しさといった東京の影はここでは光となるような。
「500人の村がゆく」には続きがある。連載翌年の2007年には「追伸 500人の村がゆく」が掲載された。2019年には統一地方選に関連させた連載「大川のほとりで 400人の村の軌跡」も記事コンテンツになった。
最新のデータによると、2021年4月現在、大川村の人口は男性182人、女性187人。合計で369人になった。「300人の村がゆく」になる日もそう遠くなさそうだ。
インターネット全盛の時代とはいえ、報道の多くは今も「東京一極集中」に傾斜している。大手マスコミの伝達力はネット時代もパワフルだ。そうした中、地域の実相を誰がどう伝えていくかは、大きな課題の一つだろうと思う。「500人の村がゆく」のように、日本の“最先端”に密着するルポが、あちこちの地域メディアに掲載されてネット上で自在に流通するようになれば、日本の自画像ももう少し違って見えるかもしれない。
(写真は大川村の公式情報サイト、高知新聞HPから)
■参考URL
「500人の村がゆく」(高知新聞)
単行本「限界集落」(曽根英二著)岡山・鳥取の県境の村を3年間密着取材した記録。山陽放送記者による作品