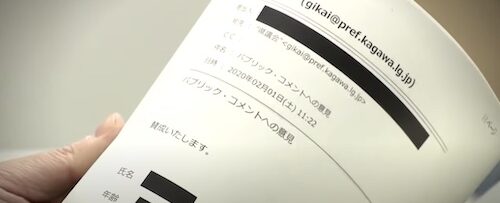「笑顔のままで 認知症―長寿社会」信濃毎日新聞(2011年)
[ 調査報道アーカイブス No.25 ]
高齢化社会にどう対応するか、認知症の患者をどうするか。これは、現代日本で最大の社会課題と言っても差し支えあるまい。高齢化社会や認知症に関するルポやノンフィクションもずいぶん増えてきた。
しかし、10年前は(既に大きな問題になっていたとはいえ)、その深刻さをわが身に引き寄せて考える人は今ほど多くなかったに違いないと思う。長野県の日刊紙・信濃毎日新聞が2010年1月〜6月にかけて手掛けたキャンペーン報道「笑顔のままで 認知症―長寿社会」は、当時としては出色の、現場感に溢れたルポだった。地域の日常、つまり、足元で起きている小さな出来事を丹念に取材し、その集積によって社会課題を浮き彫りにする手法は、地方紙の最も得意とするところだ。
このキャンペーン報道は77回に及ぶ連載が主体で、新聞協会賞(編集部門)はじめ、JCJ(日本ジャーナリスト会議)賞、ファイザー医学記事賞大賞、日本認知症ケア学会・読売認知症ケア賞特別賞を受賞した。新聞協会受賞に際しては「実名報道に徹した取材手法と平易な文章で紹介した連載は、認知症に対する価値観を転換させ、読者に共感と勇気を与えた」と評されている。
連載終了後、キャンペーンはただちに書籍化された。「認知症と長寿社会 笑顔のままで」(講談社現代新書)がそれである。筆者(高田)が当時ネット媒体の「The Journal」に書いた書評を以下に再掲しておきたい。
「更埴市」は長野県北部にあった市の名前である。近隣自治体と合併し、今は「千曲市」という。遠い遠い、30年ほど前の学生時代のことだが、このあたりを訪ねたことがある。ゼミ合宿だったか、サークルの合宿だったか。典型的な日本の田舎、地方都市だったような、おぼろげな記憶がある。
姨捨山(正式名・冠着山)は、その千曲市にある。知っての通り、姨捨山には「姨捨伝説」が残る。
年老いた母を捨てに山を登る息子。自分の息子が帰り道に道に迷わぬよう、背負われた母は登りの道すがら、手を伸ばして木の枝を順順に折っていく。それを見て、息子は母を棄てられなくなった--。そんな伝説だ。
本書は、その姨捨山近くに住む老夫婦の話から始まる。夫86歳、妻79歳。「老老」世帯の暮らしは、ただでさえ、しんどい。そこに「介護」が加わったら、いったい、どうなるか。しかも妻は認知症である。意味不明なことを話し、徘徊もする。夫が誰なのか、時にはそれも分からない。それどころか、自分がだれなのかも分かっていないかもしれない--。
私が小学校6年生の時、一緒に暮らしていた祖母が死んだ。その祖母も認知症だった。第二次大戦で死んだ息子の名前を呼んでは「さっきまで清茂がここにおった」などと言い、清茂の分の夕食を用意してないと言っては、私の母を責めた。そんな記憶がある。そして、あれだけ苦労して祖母の面倒を見て、毎日ため息をついていた母が、その祖母の死後、しばらくたって、辛かったはずの介護が実はどれだけ自分を支えていたかを語ったことがある。
当時はその意味が分からなかった。小さい子供であったから、分かるはずもないのだが、本書を読み終えた今は、母の言った意味が分かるような気もする。
本書は、新聞協会賞などジャーナリズム関係の賞を多数手にした、信濃毎日新聞の連載をまとめた1冊である。だれもが避けられぬ長寿社会。そして、かつては長い間、タブー視されていた認知症。この重い課題に真正面から取り組んだ。連載時から大評判だったので、ときどき、記事のコピーを読んではいた。しかし、こうして1冊にまとまると、また違った迫力がある。
読み始めたのは、通勤の電車の中だった。途中で落涙し、読み進めなくなる箇所もあった。各ページに事実が詰まっている。1行1行が重い。つくりが丁寧で、時間と労力を存分に費やしたことが良く分かる。
新聞はダメだ、既存メディアはダメだ、最近はそんな単純な批判が多い。しかし、本書のような良質のルポルタージュを読むと、そういった「新聞批判」を逆に空しく感じるだろう。「新聞だから悪い」とか、そんな単純な話ではないのである。何をテーマに、どう取材するか、どう伝えるか。報道においては、それが全てであり、本書はその見事な回答でもある。
写真もすばらしい。とりわけ、237ページと257ページ。この2枚の写真は、すべてを物語っている。この写真を見ると、郷里に暮らす、自分の年老いた父と母のことを思い出し、また落涙しそうになる。
■参考URL
・「認知症と長寿社会 笑顔のままで」について(The Journal)
・「認知症と長寿社会 笑顔のままで(講談社現代新書)」