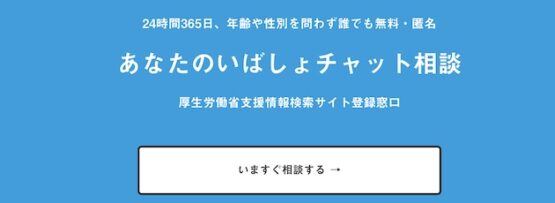◆「客観報道=当局による認定」
350通あまりの手紙が存在しているのなら、その内容をそのまま報道すればよいのではないかと考えがちだが、「報道のハードルはそんなに低くない」と秦氏は言い切る。
「報道には“客観報道”という柱があります。では、客観報道とは何か。実は、事件報道においては、客観報道とは捜査当局による認定を指していました。つまり、公的機関がある事案をどのように見ているか、それが客観性の証しだったわけです。
呼吸器事件でいうと、裁判所は7回も美香さんに対して有罪を言い渡していた。捜査機関と裁判所が、曲がりなりにも証拠に基づいて7回も判決を下しているわけです。無実を訴える手紙の束があったとしても、それらを無視して『無実を訴えている人がいる』と報道できるでしょうか」
秦氏をリーダーとする取材班は、新証拠を求めて調査報道に着手した。7回の判決はいずれも、自白の任意性と信用性を認めている。再審開始を勝ち取るには、そのポイントを突き崩すしかない。
取材班は、美香さんの幼少時や日常の言動、さらには本人が法廷で「刑事を好きになって(虚偽の)自白をした」と述べていることなどに着目し、美香さんには「発達障害」があることを明らかにしようとした。
◆「発達障害」の証明で行き詰まった取材
最初に大きな手がかりをくれたのは、美香さんの出身中学校の恩師たちだった。恩師らは「今なら(美香さんは)発達障害だと考える」と明言し、取材は進んでいく。
ただし、美香さんの発達障害を証明することは簡単ではなかった。美香さんの言動や行動履歴の資料を見た専門家からは「きちんと鑑定すれば、確実に発達の偏りが結果として出てくる」という指摘がいくつも出る一方で、「発達障害だけならウソはつかない。衝動的に殺してしまった可能性がある」との見解を示す専門家もいた。
「そこで取材は行き詰まりました。専門家のコメントは重要です。自分たちに都合のいいところだけを拝借して原稿にするようでは、ウソの供述で事件をでっち上げた警察と検事と変わりません」
もっとも、そうした専門家に用意した情報は、美香さんの成育・行動履歴のみ。虚偽自白と障害の関係についての見解を引き出すには、前提情報が不足していた。しかし、膨大な裁判資料を取材班と同じように読み込んでくれる専門家を探し出そうにも、すぐにあては見つからない。ピンチを救ったのは、絆と偶然だった。
「途方に暮れていたとき、私たちを救ってくれたのが新聞記者から精神科医に転身していた小出将則君でした。1984年に私と一緒に中日新聞に入社した同期です。7年後に退社し、信州大学医学部に進学。精神科の医師になっていました。実は、小出医師は発達障害の専門家であり、彼こそが美香さんの件で鑑定者として妥当な立場にいたのです」
小出医師は、手紙のやりとりや刑務所内での面会を通じて美香さんと接触を重ね、「発達障害のほかに軽度知的障害と愛着障害の可能性がある」と指摘。新証拠となる鑑定への道を切り開いていく。
湖東記念病院での事件は、入院男性の死亡が見つかった際、第一発見者の看護師が「呼吸器のチューブが外れていた」と警察に供述したことが発端だった。警察は自然死の疑いを考慮せず、看護師の供述が虚偽だったことがわかった後も「事件化」に向けて突き進んだ。ところが公判においても、呼吸器の「管の外れ」によるもの、とされた司法解剖鑑定書が検証された形跡がない。
「検察官や裁判官が鑑定書をちゃんと読めば、窒息死の原因として明記された『管の外れ』は他の証拠と矛盾に満ちたものであることは容易に発見できたはず。ところがそうはならなかった。原審から計7回の裁判で裁判官席に座った24人もの裁判官が、ただ漫然と見逃し続けました。
裁判官たちは、刑事が作文した『殺した』という自白調書だけを信じ、美香さんがいくら無実を訴えても、まともに証拠を読もうとしなかったわけです。検察の主張に従ってさえいればいいという日本の刑事裁判の悪しき風習と、自白偏重主義にあぐらをかく裁判官たちの嘆かわしい実態を目の当たりにしました」