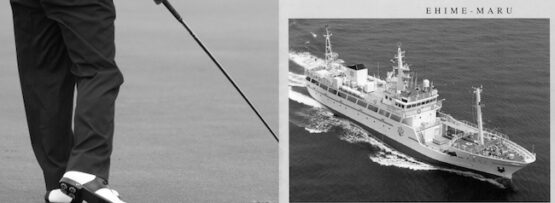◆パーキンソン病を患う80歳の夫が運転、81歳の認知症の妻が助手席に
第1部の第3回『4つの目 危険承知 決死の運転』も読ませる。
岡山県の中山間地域。細い道は山あり谷ありで急カーブも続く。その道を老夫婦はマイカーに乗り、命と隣合わせでハンドルを握る。
はた目には何の変哲もない山道だが、2人にとってはときに死と隣り合わせのドライブとなる。
「手の動きが鈍いからカーブが曲がり切れんときがあるんよ」
運転歴46年という、80歳の夫が言う。4年前に手足が震え、徐々に筋肉がこわばっていくパーキンソン病と診断されて歩行は杖(つえ)頼り。農作業もきつくなり、肥料袋も以前のようには持てなくなった。
「その時は車をバックさせて、助手席のお母さん(妻)にハンドルを切り直してもらう」
運転免許証のない妻(81)は認知症の疑いがあるが、運転時には欠かせないパートナーだ。通院や買い物に出掛ける時はいつも“4つの目”で前後左右の安全を確認しながら目的地に向かう。
道路左側の縁石に乗り上げてタイヤをパンクさせたり、タイヤホイールをこすったりと〝生傷〟は絶えないが、夫は訴える。
「危ないのはよう分かっとる。分かっとるけど、わしらにとっては杖代わり。車を手放したら生活できん」
高齢者ドライバーが悲惨な事故を起こす事例は最近、都市部でも目立つようになった。東京・池袋で母娘が亡くなった事故は記憶に新しい。その事故をきっかけにして、免許を返納する高齢者も続出した。しかし、高齢者ドライバーの問題はそれだけでは終わらない。地域には車なしでは生活できない人が多数残されているからだ。しかも、地方では高齢者ドライバーの問題が早くから顕在化していた。それなのに最近まで、必ずしも全国的な大問題にならなかったのは、「中央」に拠点を置く全国メディアが「しょせん地方の問題だ」として振り向かなかったからだ、と言えば言い過ぎか。
◆移動手段を失い、投票に行けなくなった
第1部にはこんなエピソードも出てくる。運転免許証を返納した夫(85)と妻(79)の物語だ。側溝に脱輪する事故を起こし、それをきっかけに車も手放した。すると、2〜3週間はどこにも行かない生活が当たり前になってしまった。自宅は中山間に地域にあり、路線バスのバス停は5キロ先。タクシーで山裾の町へ出ると、往復で5000円前後かかる。買い物は週に1回、土曜日にやって来る個人商店の移動販売車で済ませる。年を取ったのに、以前にも増して野菜作りに精を出す必要が出てきた。蛍光灯は1本切れたぐらいなら我慢する。散髪は出張サービスに頼んで2カ月に1度。診療所通いは月に1回、市社会福祉協議会の送迎サービスを利用する。
そんな生活に思わぬ落とし穴があった。選挙だ。連載の中で、この老夫婦の夫は語っている。
「実は選挙に行けなんでな。これまで欠かさず投票してきたのに…」と進さん。昨年7月の参院選を思い出して肩を落とした。
マイカーなしで自宅から約10キロ離れた投票所の市備中地域局までどうやって行くかー。2人の足では到底歩けない。近所の人に乗せて行ってもらう手はあるが、集落は自分たちのような高齢者ばかり。頼まれる側もかなりの重荷になるため、なかなか口には出しにくい。
タクシーという方法もあるには、ある。
「しかし、国政選挙でそこまで払ってというのが正直な思いだった」と振り返る。
結局、この老夫婦は選挙に行かなくなった。高齢者ドライバーの問題は、選挙権とも直結しているー。そんな視点を持った報道は、地域に根を下ろした地方紙だからこそ可能だったのだと思う。
『路(みち)をつなぐ 生活交通白書』は疲弊していく地域交通の実情を単に嘆くだけではない。第3部『自治体のチカラ』や第4部『インタビュー編』で、解決の方向性も見出そうとする。そして『街のはざまで』という副題の付いた第5部では、やがてこの交通問題は都市部にも波及していくだろうと見通した。実際、連載から10年を経た今、日本はこの優れたルポルタージュの見立て通りになりつつある。
■参考URL
単行本「日本の現場 地方紙で読む 2012」(花田達朗、高田昌幸、清水真編著):『路(みち)をつなぐ 生活交通白書』を一部収録
2